Pythonライブラリ「Scikit-learn」で機械学習について学ぶ際、数理的な学習を併せて行うことがおすすめな理由について解説します。
「数理的理解」とは?
「数理的理解」とは、「なぜその手法がこう動くのか」を数学を使って理解・説明できることです。具体的にまとめると以下のとおりです。
- 背後にある数学的構造を理解すること
- 線形代数(ベクトル、行列、内積など)
- 微分・最適化(誤差を最小にするための計算)
- 確率・統計(不確実性の扱いと、データの傾向を捉える方法)
- 数式で仕組みを理解すること
- 例えば、線形回帰の予測式「$ y = a x + b $」が「どうやって$a$や$b$を決定するのか」を式で理解できること
- 原理や限界を説明できること
- 例えば、「過学習とはどういう現象か?」「 予測精度が低くなったとき、何が起きているのか? 」などを数学的に説明できること
動画で見る
本ページの内容は以下動画で解説しています。
数理的理解がなくてもプログラムは動かせる
Pythonライブラリ「scikit-learn」は使いやすく、実践的な機械学習の入り口として学ぶのに適しています。
例えば、以下のように簡単なコードで機械学習を利用できます。
【サンプルコード①】身長から体重を予測
from sklearn.linear_model import LinearRegression
import numpy as np
# 学習データ(身長[cm]と体重[kg]のペア)
X = np.array([[150], [160], [170], [180], [190]]) # 身長
y = np.array([50, 60, 65, 72, 80]) # 体重
# 線形回帰モデルを作成・学習
model = LinearRegression()
model.fit(X, y)
# 予測したい身長(例:175cm)
new_height = np.array([[175]])
predicted_weight = model.predict(new_height)
# 結果表示
print(f"予測体重: {predicted_weight[0]:.1f} kg")
このように、機械学習の数理的理解、つまり「手法の仕組み」を知らなくてもプログラムを動かすことは可能です。例えば、予測したい対象が変わるならば、上記プログラムのデータ部分を修正するなど、簡単な改変で対応できます。ただし、それは 「とりあえず使える」にすぎず、「数理を理解して使える」こととは大きな差があります。
① scikit-learn の API を使ってモデルを構築・学習・予測
② グラフによる可視化(matplotlib, seaborn など)
③ チュートリアルやサンプルコードの模倣・改変
数理的理解が「必要な理由」
数理的理解がなくても、ChatGPTなどのAIツールを使ったり、自力でサンプルコード①を少し改変すれば、以下のような「広告費」から「売上」を予測するためのコードも作成できます。
【サンプルコード②】「広告費」から「売上」を予測
import numpy as np
from sklearn.linear_model import LinearRegression
# データ作成
X = np.array([1, 2, 3, 4, 5]).reshape(-1, 1) # 広告費(万円)
y = np.array([3, 4, 2, 5, 6]) # 売上(万円)
# モデル構築(線形回帰)
model = LinearRegression()
model.fit(X, y)
# 予測
new_x = np.array([[7]])
new_y = model.predict(new_x)
# 結果表示
print(f"予測売上: {new_y[0]:.1f} 万円")
ただし、数理的理解が不足していると、
① パラメータ(係数や切片など)の意味は「なんとなく」しか分からない。
② 予測精度が悪いときの根本原因「なぜ?」が分からない。
③ そもそも使っている手法は適切なのか?見込みがあるのか?が分からない。
といったことに陥りがちです。数理的理解が不足した状態で、「scikit-learn」のような便利ツールで機械学習を利用したときの問題点をまとめると、以下のとおりです。
- 手法の選定ができない
- 機械学習には様々な手法がありますが、数理的理解がないと、各手法の前提条件や構造がわからず、解決したい問題に適した手法をうまく選定できません。
- チューニングが手探りになる
- 機械学習を使用する過程で、精度を向上させるためにチューニング(パラメータの調整)が必要となります。
- 数理的理解がないと、パラメータの意味や結果に対する影響が分からず、調整が手さぐりになります。
- 相手に説明できない
- 数理的理解がないと、成果物(「なぜその結果になったのか」「なぜこの手法が優れているのか」など)説明できません。
- 論理的な妥当性を相手に説明できなければ、成果物の信頼性が乏しく、提案が通るのは難しいでしょう。
- 仮に提案が採用されたとしても、精度だけで判断(ブラックボックス化)することとなり、実用性や安全性を見落とすリスクがあります。
- 関係者(エンジニア、データサイエンティスト、顧客など)との会話が噛み合わず、誤った意思決定に繋がるリスクがあります。
- 新しい手法の理解ができない
- 数理的理解がないと、数式ベースの説明が多い、最新技術に関する「論文」や「解説書」を正確に把握することが難しいです。機械学習の分野は進化が激しいため、新しい手法を常にウォッチし、正確に捉えることが重要です。
AIツール(ChatGPTなど)とPythonを使えば、数理的な理解がなくても機械学習は利用できますが、実務や研究等で使用するには数理的な理解を深めることも大切です。
例えば、サンプルコード②で使用している線形回帰モデルは「最小二乗法」を用いて「予測値と実測値の差(残差)」の二乗和を最小にするように学習します。
$$ \sum_{i=1}^{n} (y_i – (a x_i + b))^2 $$
「最小二乗法」を数理的に理解していると、「線形回帰モデルは、なぜ外れ値に弱いのか(外れ値の除去が必要なのか)」ということも論理的に解釈し、精度が悪くならないような上手な使い方ができます。
① scikit-learnなどのツールの出力結果を鵜呑みにせず、「このモデルはなぜこの結果を出したのか?」「この予測は信頼できるのか?」と批判的に検証できる
② 高精度化するためにデータを整理したり、問題解決に適した手法を選び直すなどが自分でできる
③ 「このモデルはこういう数理的根拠で選びました」と、他者に説明・説得できる(論理的に説明できる人は、意思決定の場にも呼ばれるようになります)
おすすめの学習方法(数理を避けすぎない)
機械学習を学ぶうえで数理的理解は重要ですが、「すべてを完璧に理解する」必要はありません。例えば以下のように、各手法のコアとなる数理を学ぶのが効率的です。
- まずは、Pythonライブラリ「scikit-learn」など、使いやすいサンプルコードを動かしてみる
- 機械学習を実装するときの、大まかな流れ(データ作成→モデル構築→学習→予測→精度検証→チューニング)の感覚を掴みます。
- 結果に疑問をもつ
- 「なぜこの精度?」「なぜこの手法が強い?」「なぜこのパラメータを調整したら結果が良くなる?」など、結果に疑問点をもつ。
- 各手法のコアとなる数理を学ぶ
- 各手法の仕組みを理解するうえで必要な数理的な基礎知識(統計・線形代数など)を学ぶ。
- 各手法の仕組みのコアを数理的に理解する。(例:回帰分析なら「最小二乗法」など)
- サンプルコードを動かしたときの疑問点を数理的に理解する。(例:「なぜ回帰分析は外れ値の悪影響を受けやすいのか」など)
数理的な学習だけを行うと挫折しやすいですが、Pythonライブラリ「scikit-learn」の使い方と併せて学習することで理解が進みやすくなります。最初は難しく感じるかもしれませんが、数理的な理解が深まると、以下のようなことができるようになり、「AIを使う人材」としての価値を高めます。
「AIツールを使うだけで完結する仕事」は、やがてAIに代替されていくでしょう。一方で、「論理的にAIツールを選定・調整できる仕事」は、今後ますます価値を高めていきます。
AI時代を生き抜くためには、ツールの操作にとどまらず、その背後にある数理的な仕組みや原理を理解することが不可欠です。使い方を覚えるだけで満足せず、理論を深く掘り下げる姿勢こそが、技術を真に使いこなす力へとつながります。
| 自動化されやすい仕事 | AIに代替されにくい仕事 |
|---|---|
| 定型的なデータ入力・集計 | 問題設定・仮説構築・モデル設計 |
| 単純な予測・分類 | モデルの選定・評価・改善 |
| マニュアル通りの作業 | 創造的・戦略的な判断 |
以下ページでは、Pythonライブラリ「scikit-learn」の使い方を数理的な背景も含めて解説していますので、是非ご一読ください。

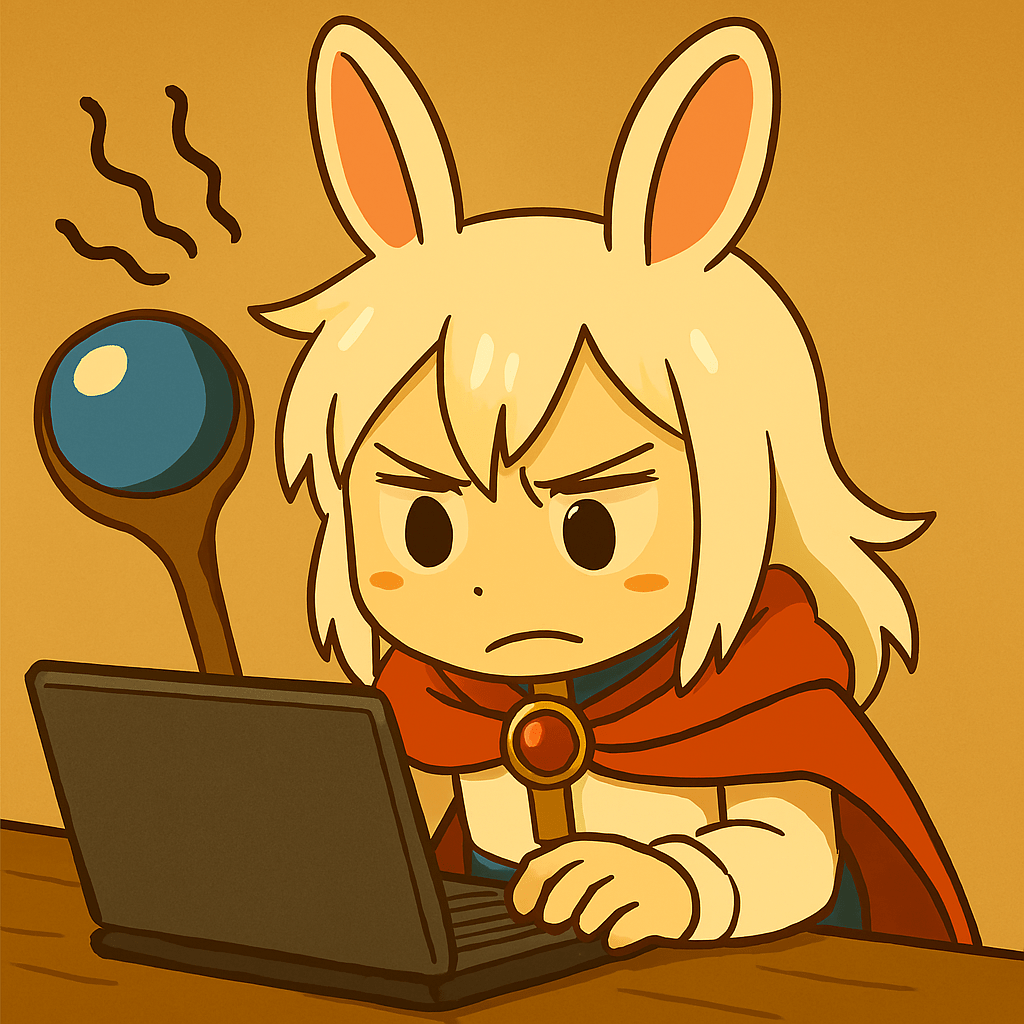


コメント